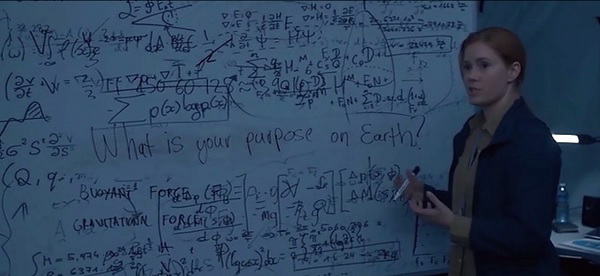反田恭平が2位、小林愛実が4位という素晴らしい栄誉となった第18回ショパン国際ピアノコンクールをYouTube配信で連日見ながら、ショパンのことをあまり知らないなとAmazonプライム・ビデオで見つけたので見てみました。
ショパンの生家とそっくり組まれたセットから始まります。映画の中ではショパンの才能を見出したエルスナー教授とショパンの師弟物語という構成になっている。教授というには人格破綻しているキャラクターにいささかイライラしっぱなしです。こんな先生の元ではまともな生徒なんか出てこないぞと思い、あまりの無茶な展開に見るのをやめようかと何度も思いつつ、日を分けて3日ほどかけてやっと見終わったという無茶なレビューです。
登場人物は数人。無理矢理まとめると登場人物3人でなんとか説明できる映画となっている。エルスナー教授、ショパン、ジョルジュ・サンド。1h53minの尺ではっきりいって1時間25分頃まではおっちょこちょいで自分勝手なエルスナー教授、恋人で同棲しているというのに夫人という呼称のままのサンド、その間でふらふらしていて正直何考えているのかわかるようなわからないような巻き込まれキャラのショパンの物語。
この映画が一体どこに向かおうとしているのか全くわからないままその1時間半くらいまで進むと映画が一転する。それがポーランド暴動のニュース。歴史的には実際どういうものだったのかは調べていないのでわからないけれど、ただそこで三人の考え方が決定的に分かれてしまう。そしてこれこそがこの映画のテーマなんじゃないかという考えに至りました。
日本では命が一番大切、一番大切なものは命であって命の尊さを知るというのが絶対的価値になっている。それは本当にそうなのだろうかというのがこの映画にある。
小説家でもあるサンドは、芸術家の使命は多くの芸術作品を世に残すことであると考えている。そのためには生きていかなければ作品も残せない。死んでは元も子もない。
対してエルスナー教授は祖国への愛である。自分が生きているのは途絶えることなく続いてきた自分の先祖であり、そのご先祖さまを守ってきたのは祖国である。祖国を蔑ろにしてまで生きていく価値はないという考え方なんだろうと思う。
つまり命が一番と考えるサンドと、命よりも大切なものがあると考えるのがエルスナーの話なのです。
そう考えて最後の25分を見るとそれまでドリフのコントのようなシーンも多い映画が急に輝いてきます。
自分の仲間が殺されていくのを知りつつそれに目を閉ざして自分の芸術作品を生み出すことが正しいことなのか。もし自分には僅かかもしれないけれどそれを救う手立てがあるのであればもしかしたら自分は命を落とすかもしれないけれど、やってみようという気持ちと行動を起こすのかどうするのか。
映画の中でサンドは天才作曲家の使命は曲を残すことでありショパンはポーランドという小国を超えた人類のために人生を全うすべきであると考える。
ショパンは祖国の同志を裏切って得た人生は本当のものではない、祖国のためにもしすべきことがあるのであれば、それをしなければ魂を売ってしまうことと同じだという考えに至る。
このストーリーがショパンの伝記なのかという疑問はあるが、映画としてはそこをテーマに描いている。もっというなら、このテーマを描くためにショパンという題材を選んだように思える。なぜなら、事実とはおそらく異なるエピソードや人物描写が多すぎるように思ったからだ。
この映画は1945年1月に公開されている。つまりはまだナチスが持ち堪えているころで、ナチスがユダヤ人大虐殺を行っていることが広まってきた頃だと思う。そんななかで、言葉悪いが呑気にショパンの伝記映画を作ってる暇はない。いや、ショパンを描くことで国家、あるいはスラブ民族の魂を声高く唱えようとしたのではないか。そんな映画に思えました。
原題の “A Song To Remember” は自分が高校入学時に学校から渡された楽譜集のタイトルでもありましたとさ。
関連サイト▶︎
IMDb